固定資産税を払っていない土地はどうなる?差し押さえのリスクと回避する方法
目次
1.はじめに
土地を所有していると、必ず毎年課されるのが「固定資産税」です。固定資産税は自治体の財源として重要な役割を担う税金であり、所有している限り必ず納める必要があります。しかし、相続などで突然土地を取得した方や、活用できていない更地を持っている方にとって、固定資産税は「収益を生まないのに出費だけが続く負担」と感じやすいものです。
中には、「固定資産税を払わないで放置したらどうなるのか?」と疑問を抱いたり、実際に支払いが遅れて不安を感じている方も少なくありません。税金の滞納は放置すればするほどリスクが高まり、最悪の場合は大切な土地を失う事態にまで発展してしまいます。
この記事では、固定資産税を払っていない土地にどのようなリスクがあるのか、延滞金や差し押さえ、公売といった具体的な流れをわかりやすく解説します。そのうえで、「払えないときにどうすればいいのか」という現実的な対処法や、土地を活用して固定資産税をまかなう方法についても詳しく紹介します。
2.固定資産税を払わないとどうなる?

固定資産税を滞納したからといって、すぐに土地を失うわけではありません。しかし、滞納を続けるほど延滞金は増え、やがては財産の差し押さえや公売(こうばい)へと進み、最終的に土地そのものを失うリスクが現実化してしまいます。ここでは、実際にどのような流れでリスクが高まっていくのかを、制度や数字に基づいて具体的に解説します。
2-1.延滞金の発生
納期限を過ぎると、まず課されるのが「延滞金」です。これはいわゆる利息のようなもので、支払わなかった税額に加えて法定利率に基づく延滞金が加算されます。
地方税(固定資産税を含む)の延滞金は「特例基準割合+7.3%」で計算され、上限は年14.6%と定められています。実際には、納期限を1か月以内に過ぎた場合は比較的低い利率(例:年2〜3%程度)ですが、1か月を超えて滞納すると最大で年14.6%まで上昇します。
たとえば10万円の固定資産税を滞納し、1年以上放置した場合、延滞金だけで1万円以上が追加されることも珍しくありません。数年間滞納を続ければ「本来の税額より延滞金の方が高くなる」という事態も現実に起こります。
延滞金の計算は「滞納額 × 経過日数 × 利率 ÷ 365」で行われるのが基本です。小額滞納(例えば2,000円未満)の場合には延滞金が課されない自治体もありますが、ほとんどの場合は利息のように日々加算されていくため、放置するほど負担が雪だるま式に膨らんでいくのです。
2-2.財産の差し押さえ
延滞が続き、督促状や催告書を受け取っても支払いをしない場合、市区町村は「財産の差し押さえ」に踏み切ります。
差し押さえの対象は多岐にわたり、預貯金や給与債権、生命保険、不動産などが含まれます。特に土地や建物といった不動産は換価(売却して現金化)しやすいため、自治体が差し押さえを実行する可能性は高い資産です。
法律上は、督促状を発した日から10日を経過すれば差し押さえ可能とされています。ただし実際の運用では、自治体が段階を踏んで予告通知や面談を行うケースが多いものの、滞納を続けている限り、差し押さえのリスクは確実に高まっていきます。
一度差し押さえられると、不動産登記簿に「差押」の記録がなされ、自由に売却することも難しくなります。滞納を抱えたままでは相続や土地活用の手続きにも支障が出るため、この段階に至る前に必ず解決を図るべきです。
2-3.公売(競売)による強制換価
差し押さえ後も滞納が解消されない場合、最終的には「公売(こうばい)」に進みます。これは自治体が主導して差し押さえた財産を売却する制度で、裁判所の「競売(けいばい)」とは手続きの主体が異なります。
公売では、入札やインターネット公売を通じて第三者に土地が売却されます。売却代金は、まず延滞している税金や延滞金、手続き費用に充てられ、残額があればオーナーに返還されます。しかし、一般に公売での売却価格は市場価格より低くなる傾向があり、実質的には土地を「安く手放す」ことになってしまうリスクが高いのです。
つまり、固定資産税を長期的に払わないまま放置すれば、最終的には大切な土地を強制的に失うことにつながります。たとえ先祖代々の相続土地であっても、税金を払わなければ守れません。
3.固定資産税が払えないときの対処法
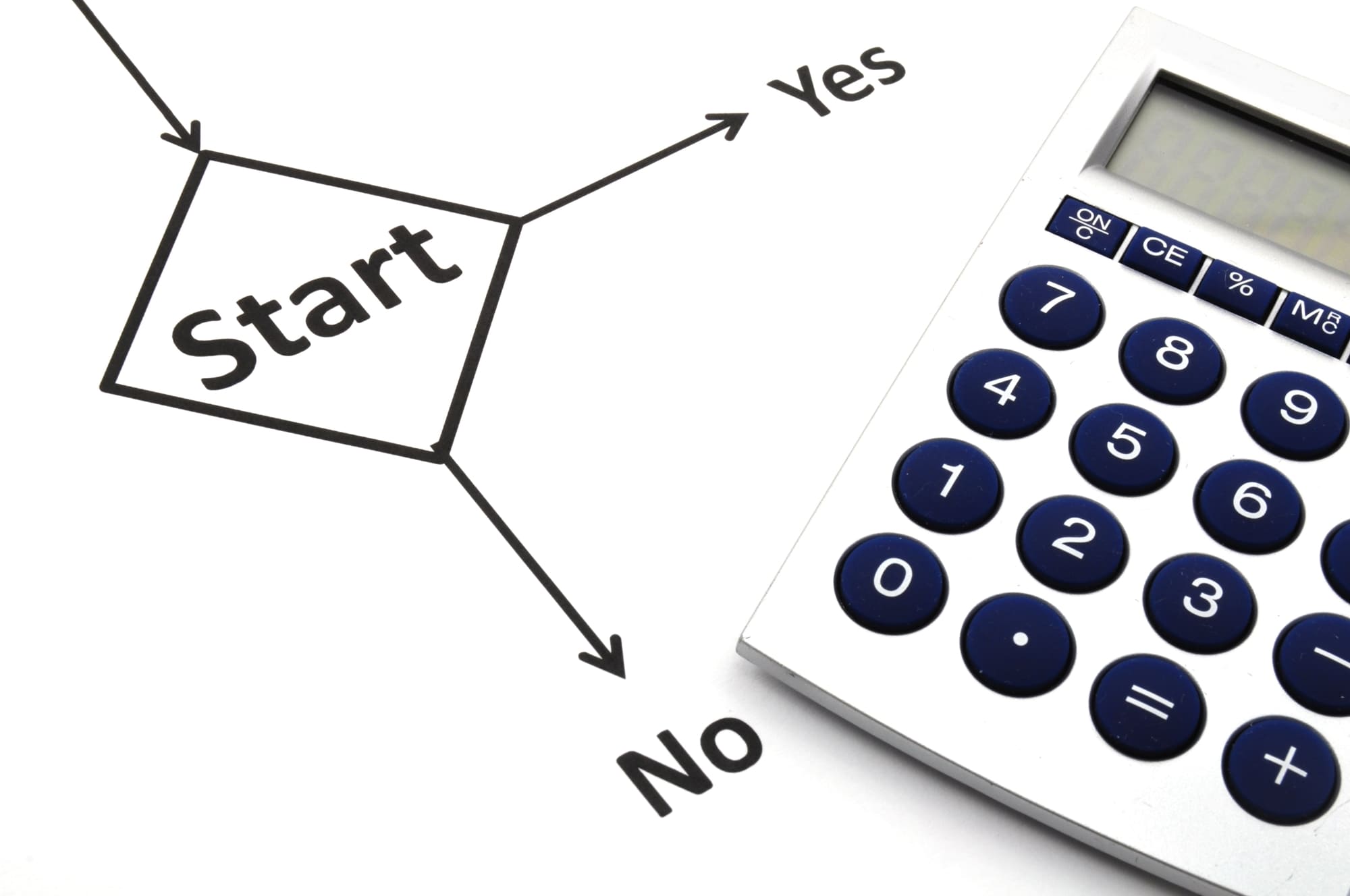
「払わないと危険なのはわかっている。でも、どうしても払えない…」そんな場合に取れる選択肢はいくつかあります。大切なのは、放置せずに早めに動くことです。
3-1.猶予や分割払い制度を活用する
固定資産税は基本的に一括払いが原則ですが、自治体に相談すれば「分割払い」や「納税猶予」の制度を利用できるケースがあります。たとえば、災害や病気、事業不振などやむを得ない事情がある場合には、延滞金の減免や猶予が認められることもあります。延滞が深刻化する前に、必ず市区町村の税務課へ相談しましょう。
3-2.相続した土地は収益化を検討する
特に相続で引き継いだ土地は、収益を生まないまま固定資産税だけが発生し続ける「負の遺産」となりやすいものです。こうした土地をそのまま放置するのではなく、早めに活用方法を検討することで、固定資産税を補えるだけでなく、収益を得るチャンスに変えることができます。
3-3.売却・賃貸という選択肢
どうしても活用が難しい場合には、土地を売却して納税資金を確保する選択肢もあります。また、一時的に賃貸に出すことで収益を得て、その収益から固定資産税を支払う方法も考えられます。いずれにせよ「払えないから放置」するのではなく、資金を作る手段を探すことが最も重要です。
4.土地活用で固定資産税をまかなう方法
固定資産税をまかなうための根本的な解決策は、「土地を収益化すること」です。収益があれば、そこから税金を払うことができ、負担から解放されます。ここでは代表的な土地活用の方法を紹介します。
4-1.アパート経営・トランクルームなどの選択肢
土地活用と聞くと、アパートやマンション経営を思い浮かべる方も多いでしょう。確かに収益性は高いですが、多額の建築費用が必要で、空室リスクも大きな課題です。他にはトランクルーム経営といった活用法もありますが、いずれも初期投資や運営の手間がかかるため、すべての土地に適しているとは限りません。
4-2.初期費用が少なくリスクも低い「駐車場経営」
そこで注目されているのが「駐車場経営」です。駐車場経営は建物を建てる必要がなく、更地からでも手軽に着手できるため、他の土地活用方法に比べて初期投資を大幅に抑えられるのが魅力です。特に都市部や駅周辺では需要が高く、小規模な土地でも収益化しやすいのが特徴です。また、舗装や精算機を導入すればコインパーキングに、簡易的な区画線を引くだけで月極駐車場にできるなど、土地の状況に応じて柔軟に始められる点も魅力です。
駐車場経営で得た収益をそのまま固定資産税に充てれば、「自分が働かなくても土地に働いてもらう」状態を作れます。
5.一括借り上げ方式なら安心して税負担を解消できる

駐車場経営にはいくつかの運営方式があり、それぞれに特徴とリスクがあります。代表的なのは「自主管理方式」「委託管理方式」「一括借り上げ方式」の三つです。いずれの方式を選んでも収益を得ることは可能ですが、固定資産税をまかなうことを目的とするなら、安定性の違いが大きなポイントになります。ここでは三方式を整理しながら、一括借り上げ方式がなぜ安心できるのかを確認していきましょう。
5-1.自主管理方式
自主管理方式は、オーナー自身が駐車場のすべてを直接管理する方法です。契約書の作成や賃料の回収、清掃や修繕、利用者とのトラブル対応まで自分で行うため、管理費がかからず収益性は高くなります。
しかし、その反面「空車リスク」をすべてオーナーが負うことになります。駐車場利用者が集まらず稼働率が下がれば、収入が減り、固定資産税を払うための資金すら不足しかねません。また、クレーム対応や未払い利用者への対応など、精神的な負担も大きく、本業を持つ方や相続で突然土地を引き継いだ方にとっては現実的に難しい場合も多いでしょう。
5-2.委託管理方式
委託管理方式では、日常の清掃や集金、利用者対応などを管理会社に任せられるため、オーナーの手間は大幅に減ります。その分、売上の一定割合(一般的には10〜20%前後)が管理委託料として差し引かれます。
確かに「管理の負担が軽減される」という点では魅力的ですが、空車リスクは依然としてオーナーが負います。つまり、利用率が下がれば収入が減り、固定資産税をまかなえない月が出てくる可能性は十分にあるのです。収益と安定性の両方を求める方にとっては、やや不安の残る方式といえます。
5-3.一括借り上げ方式
一括借り上げ方式は、管理会社が駐車場全体をまとめて借り上げ、オーナーに毎月固定の賃料を支払う仕組みです。最大の特徴は、空車リスクをオーナーが負わなくてよいという点にあります。実際の稼働率に関わらず一定額が支払われるため、固定資産税を安定的にまかなうことができるのです。
さらに大きなメリットは、初期投資を管理会社が負担してくれるケースが多い点です。精算機やゲート、照明や防犯カメラ、さらには舗装工事まで、通常なら数百万円単位でかかる初期費用をオーナーが用意する必要がありません。土地を提供するだけで駐車場経営が始まり、すぐに固定資産税を支払うための仕組みを整えることができます。
また、日常的な清掃や利用者対応、トラブル解決まで管理会社が担当するため、オーナーは実質的に「土地を貸しているだけ」で済みます。本業に集中したいサラリーマンオーナーや、相続で土地を取得した方にとって、この仕組みは極めて安心感が大きいといえるでしょう。
5-4.安定収益を重視するなら一括借り上げ方式
自主管理方式は収益性が高い一方でリスクと手間が重く、委託管理方式は手間は減るが収益の変動リスクが残ります。それに対して一括借り上げ方式は、空車リスクを負わず、初期投資や日常管理の負担もほとんどありません。
特に「固定資産税を確実にまかないたい」「差し押さえや滞納のリスクを避けたい」と考える方にとって、一括借り上げ方式は現実的で安心感のある選択肢といえるでしょう。
6.まとめ
固定資産税を払わない土地は、延滞金の発生から始まり、差し押さえや公売に至るまで深刻なリスクを伴います。しかし、払えないからといって放置するのではなく、猶予や分割払いを利用したり、土地活用によって収益を生み出すことで解決できます。
中でも駐車場経営は、初期費用が少なく更地でも始めやすいため、固定資産税をまかなう現実的な方法です。そして一括借り上げ方式を選べば、初期費用がほぼゼロ・空車リスクなし・管理不要というメリットにより、安定収益を確保しながら税負担を安心して解消できます。
- 「土地を守りながら無理なく固定資産税をまかないたい」
- 「手間をかけずに安定した収益を得たい」
そう感じた方は、一度NTTル・パルクにご相談ください。これまで全国で培ってきた豊富なノウハウを活かし、オーナー様それぞれの土地状況に合わせた活用プランを提案し、安心して長期的に土地を維持できる仕組みをサポートします。

 駐車場経営を
駐車場経営を お問い合わせ
お問い合わせ






