駐車場経営でかかる経費とは?節税効果と負担を減らす方法を紹介
1.はじめに
土地を所有している方にとって、「固定資産税の負担を軽くしながら土地を活かす」ことは長年の課題です。その中で駐車場経営は、建物を建てずに始められる手軽な土地活用として注目されています。
しかし、いざ始めてみると「意外と維持費がかかる」「節税になると聞いたが、現金が減っていく」と感じるオーナーも多いのが実情です。経費は節税に有効ですが、その分の支出は現金流出を意味します。やみくもに経費を増やせば、キャッシュフローの悪化を招くこともあるため、計画的な支出管理が必要です。
この記事では、駐車場経営における経費の種類とその扱い方、節税効果の正しい理解、さらに経費を抑えて安定収益を得るための方法までを詳しく解説します。
2.駐車場経営で経費にできるもの・できないもの
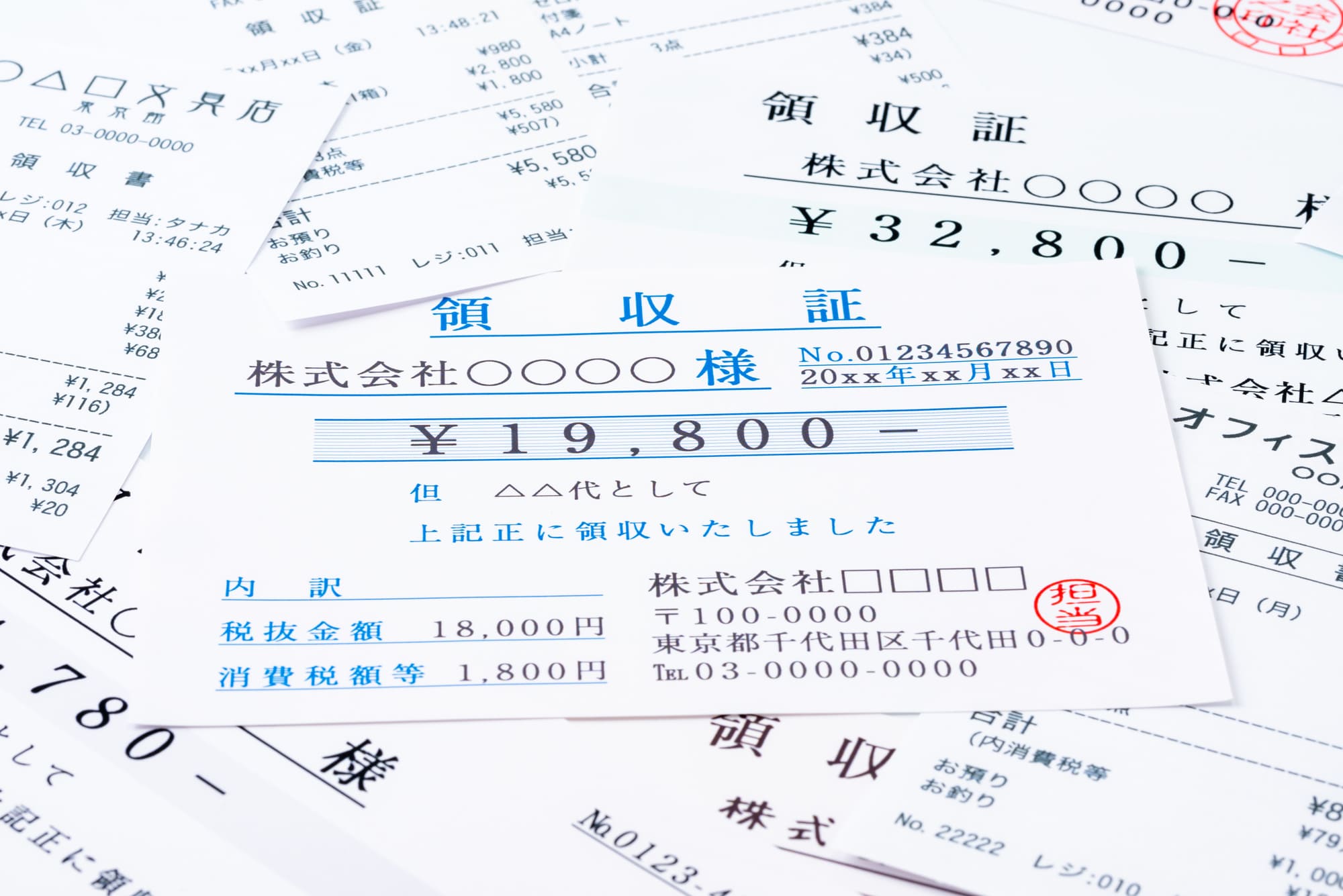
駐車場経営における「経費」とは、事業を運営するうえで直接必要な支出を指します。しかし、税務上は「どの範囲までが経費に該当するのか」を正しく理解していないと、余計な出費や申告ミスを招くおそれがあります。ここでは実際のオーナーがよく悩むポイントを踏まえて、経費の具体例と注意点を詳しく見ていきましょう。
2-1.経費にできるもの
2-1-1.固定資産税・都市計画税
まず最も代表的なのは「固定資産税」と「都市計画税」です。土地を所有している限り必ず発生するもので、駐車場経営では毎年のコストとして計上できます。たとえば150㎡の土地を都市部に所有している場合、年間の固定資産税・都市計画税を合わせて15〜20万円前後負担しているケースが多く、この金額は全額経費になります。
2-1-2.設備の減価償却
さらに、コインパーキングの場合は「設備投資」に関連する減価償却費が大きな割合を占めます。ロック板や精算機、防犯カメラ、LED照明、看板などの設備は購入時に数十万〜数百万円単位の支出が発生します。たとえば、10台分のコインパーキングを新設する場合、初期設備費として約500万円が必要ですが、税務上は耐用年数に応じて分割して経費化できます。この減価償却は節税効果が高く、実質的に「支出を複数年に分散する」ことで利益を平準化できます。
2-1-3.管理・清掃・保守費用
また、運営面では「管理委託料」「清掃費」「保守点検費」「防犯カメラの通信費」なども経費に含まれます。これらはすべて“事業継続に不可欠な支出”として処理できます。たとえば週2回の清掃委託を月2万円、精算機点検を月1万円とすれば、年間で36万円程度。これらも全額経費にできます。
2-1-4.保険料・広告宣伝費
駐車場で事故が発生した場合に備える「施設賠償責任保険」や「火災保険」の保険料も経費です。また、新規利用者を増やすために設置した看板広告や近隣チラシの印刷費用なども、駐車場の収益維持を目的とした支出として認められます。
2-2.経費にできないもの・注意が必要なもの
2-2-1.私的利用を含む支出
明確に事業と関係していない支出は経費になりません。例えば、自宅敷地内にある駐車スペースを一部だけ貸している場合、その敷地全体の税金や修繕費を経費にしてしまうのは誤りです。あくまで貸している面積分だけが経費の対象です。
また、個人利用の車両の燃料費や車検費用も、駐車場経営に直接関係がなければ認められません。「集金や巡回に使う車両」として明確な根拠がある場合のみ、按分して経費にできます。
2-2-2.私有地の整備・外構工事
駐車場として使う目的で舗装したり、ラインを引いたりする工事は経費にできますが、自宅の外構や庭の整備など、事業以外の目的を含む工事は対象外です。特に「見た目をよくするためのリフォーム」「家屋側の外壁塗装」といった費用は経費とは認められません。
2-2-3.過剰な接待・通信費・備品
携帯電話料金や事務用品なども、駐車場経営に必要な範囲内であれば経費になります。しかし、実際には事業でほとんど使っていない場合や、私用が中心の場合は否認されることもあります。たとえばオーナー1人の経営で月3万円の通信費を計上している場合、明細の提出を求められる可能性があります。
2-2-4.税務上グレーな支出
「駐車場経営を検討するための旅行費」「視察を兼ねた出張」などは、内容次第では経費にできますが、証拠書類が不十分だと認められないケースが多いです。経費にする場合は、目的や内容をメモし、領収書と一緒に保管しておくことが重要です。
2-3.経費は節税につながるが、現金支出にも注意
経費を計上すれば所得が減り、結果的に税負担は軽くなります。しかし、それは同時に「現金を使った」ということでもあります。たとえば50万円の修繕費を支払えば税金は10万円ほど減りますが、実際には40万円が手元から出ていきます。節税を優先しすぎると、手元資金が不足し、キャッシュフロー(資金繰り)が悪化するリスクがあります。経費は「使うためのもの」ではなく、「利益を守るための支出」です。目的を明確にし、必要なものにだけお金を使うことで、結果的に経営の安定と節税の両立が実現します。
このように、「経費にできる・できない」の判断は、“その支出が駐車場経営の収益維持に直接関係しているか”によって決まります。税務署は領収書や契約内容といった根拠資料を重視するため、支出の記録を丁寧に残すことが、安心して経営を続けるための第一歩です。
ただし、経費の判断はケースによって異なります。とくに、自宅と駐車場が併用されている場合や、一部のみを貸しているケースでは、私的利用と事業利用の線引きが曖昧になりがちです。迷ったときは税理士に相談し、どの支出を経費として計上できるのかを、実際の事例をもとに確認しておくと安心です。正しい処理を行うことで、税務上のトラブルを未然に防げるだけでなく、節税効果を最大限に活かすことができます。
3.経費のメリットとデメリット

経費を計上することには確かにメリットがありますが、それと同時に注意点もあります。節税という短期的な視点だけでなく、経営全体に与える影響を正しく理解する必要があります。
3-1.節税効果で利益の最適化が可能
経費を計上することで所得が減り、結果的に税金の負担を軽減できます。たとえば、年間収入が300万円で経費が100万円の場合、課税対象は200万円です。所得税・住民税を合わせた実効税率が20%なら、税額は40万円。もし経費を計上せずに300万円すべてを所得とした場合、税額は60万円になります。つまり、経費を正しく処理することで20万円の節税効果が得られるのです。
このように、経費は「利益を調整し、税負担を最適化するための経営手段」として機能します。
3-2.支出増加によるキャッシュフローの悪化
一方で、経費が増えれば支出も増えます。節税を目的に設備を更新したり修繕を頻発させたりすると、短期的に出費が膨らみ、現金残高が減少します。経費を増やすことは「お金を使って税金を減らす」という行為であり、利益を守るためにはキャッシュを優先的に確保する姿勢が欠かせません。
「節税のための支出」は長期的には経営を圧迫します。必要な経費だけを計上し、支出のタイミングを分散させることで、キャッシュフローを安定化させましょう。
3-3.黒字でも資金が足りない「利益と現金のズレ」
駐車場経営では、帳簿上は黒字でも資金が足りないという「黒字倒産」に似た現象が起こりやすいです。その原因は、税金や修繕費などの支払いが集中する時期に現金が不足するためです。このズレを防ぐには、毎月の収入から将来の修繕・税金分を積み立て、一定の資金を常に確保しておくことが大切です。
4.経費を抑えつつ安定収益を得る方法
経費を減らせば手元資金は増えますが、過剰な節約は品質や利用率の低下につながるおそれもあります。駐車場経営で求められるのは、「支出を減らすこと」ではなく、「支出の効果を最大化すること」です。そのためには、運営方式や契約形態を見直して、効率の良い支出構造をつくることが欠かせません。
4-1.自主管理と管理委託の違いを理解する
駐車場経営には、大きく分けて「自主管理」と「管理委託」の2つの運営方法があります。自主管理は、オーナー自身が清掃・集金・クレーム対応を行う方式で、外注費がかからない分、経費は最も低く抑えられます。たとえば10台規模の月極駐車場なら、年間維持費は10万円以下で済むこともあります。
一方、管理委託方式では、清掃・点検・トラブル対応を管理会社に一括で任せます。月に収益の10〜20%前後の委託料がかかりますが、手間をかけずに安定運営を続けられるのがメリットです。特に遠方の土地を活用するオーナーにとって、時間的コストやトラブル対応のストレスを考えれば、委託料は“安心の対価”ともいえます。
ただし、管理委託を利用しても、精算機の故障や照明の交換など突発的な修繕費はオーナー負担となる場合が多い点に注意が必要です。そのため、委託料を払っても、運営上のリスクを完全に消すことはできません。
4-2.設備更新・修繕費の負担に注意
経費の中でも特に重いのが「設備の修繕・更新費」です。精算機やロック板は消耗品であり、耐用年数を過ぎると故障や通信エラーが発生します。メーカーや機種にもよりますが、精算機の耐用年数はおおむね8〜10年、ロック板は5〜7年が目安です。仮に精算機を1台60万円で導入した場合、10年後には再投資が必要になります。10台規模の駐車場なら、更新費用だけで数百万円にのぼるケースも珍しくありません。こうした費用は、売上の波に関係なく突発的に発生するため、毎年少しずつ積み立てて備えるのが理想です。
また、照明・舗装・看板の更新も経年劣化によって発生します。アスファルトのひび割れ補修に数十万円、防犯カメラ交換に10万円程度など、定期的な出費は避けられません。これらを「想定外」とせず、年単位で費用化しておくことが、結果的に経営の安定につながります。
4-3.経費を固定化し、収支を安定させる
駐車場経営では、経費の“ブレ幅”がキャッシュフローを不安定にします。毎月の管理費や清掃費、通信費などを定額契約に変更することで、支出を平準化できます。また、定期点検を年間契約にすれば、突発修繕の発生率を下げ、長期的な支出を抑える効果もあります。
実際、経費を固定化しているオーナーとそうでないオーナーでは、年間キャッシュフローに約15〜20%の差が生じるといわれています。支出を見える化し、契約を固定化することで、経費を抑えながら安定した収益を得られます。
経費や税金の負担だけでなく、駐車場経営で後悔しない委託会社選びも大切です。詳しくはこちらをご覧ください。
5.経費構造を変える「一括借り上げ方式」

経費負担を減らしたいオーナーの間では、「一括借り上げ方式」という管理方式が選ばれています。この方式は、運営会社が土地を借り上げ、オーナーに毎月一定の賃料を支払う仕組みです。オーナーは設備費や管理費、修繕費などをほとんど負担せず、安定した家賃収入を得られるのが最大の特徴です。
5-1.経費削減の仕組み
一括借り上げ方式では、運営会社が土地を借り受けてコインパーキングなどを設置・運営します。この方式では、設備投資の多くを運営会社が負担し、管理業務(清掃・集金・メンテナンスなど)も同社が担当するので、オーナーは土地を貸すだけで収益を得られます。
そのため、オーナー側の経費は「固定資産税」と「所得税の申告費用」程度に限られ、年間経費が数十万円から数万円規模まで減少します。結果として、手取り収益率(キャッシュフロー)は自主管理型よりも高くなる傾向があります。
5-2.安定した固定収入のメリット
一括借り上げ方式の大きなメリットは、「収入の安定性」です。利用者数にかかわらず毎月固定の賃料が入るため、稼働率に左右されません。たとえば月額10万円の契約なら、満車であっても空車であっても同額の収入が保証されます。また、メンテナンスや修繕リスクを会社が負担するため、突発的な支出も発生しません。「支出がなくても収入が一定」という仕組みが、駐車場経営をより安定した資産運用へとつなげます。
5-3.副業・相続対策としての有効性
一括借り上げは、特に副業として土地活用を検討する会社員層や、相続対策を考える高齢オーナーにも向いています。土地を所有しているだけで発生する固定資産税を、リスクを取らずにまかなえる点が評価されています。また、将来的な相続時にも「安定した賃貸収入がある土地」として評価されやすく、資産価値を維持しやすいというメリットもあります。こうした点から、一括借り上げ方式は“節税を超えた経営効率化”の手段として、近年再評価されています。
6.まとめ
駐車場経営では、清掃費・修繕費・税金・管理費など多くの支出を経費として計上できますが、節税だけを目的に支出を増やすのは危険です。経費は「事業を維持するためのコスト」であり、無駄を省きながらキャッシュフローを健全に保つことが、長期的な成功につながります。
特に、経費負担を最小限に抑え、安定収益を得たい場合には「一括借り上げ方式」が有効です。初期費用を抑えつつ、設備管理や修繕のリスクを回避できるため、オーナーは固定の収入を確保しながら安心して土地を活用できます。
- 「この土地で採算が取れるのか?」
- 「費用をかけずに、不安なく始められる方法はどれ?」
こうした疑問をお持ちなら、NTTル・パルクにご相談ください。大切な土地を安定した収益源へと変えるための最適なプランをご提案します。

 駐車場経営を
駐車場経営を お問い合わせ
お問い合わせ






